座標を使って面積を求める方法をLECの講座で習った。
土地家屋調査士試験では特Aランクに重要な項目と思われる。
特Aというよりは、人間が息をするくらい普通にやらなければならない作業とも思える。
木村先生が言うように、理屈で覚えるのではなくて、「身体で覚える」くらいになりたいものだ。
けども、何度かやったが、必ず「ひっかかる点」があるので、いまのうちになんとかせんといけん、と思いまとめた。
あくまでわたしのクセだけども、誰かの役に立つかもしれんから書いておく。
独立メモリーに登録するのを忘れる
講座では、単に理論を一方的に教えてもらうわけではなく、関数電卓の操作まで手取足取り教えてもらえる。
独学だと、こんなことまで書いてある本はないだろうから、この点は予備校生としてはありがたい。
いくつかの式を最後に足し算して座標法は求めるが、その時に「独立メモリー」というに値をぶっこんで自動的に足していく昨日を使う。
これを登録するのをうっかり忘れるのだ。
かなり危険だ。いまはせいぜい4つくらいだからいいけども、点数が多くなると、「はて?いま登録したっけ?」となるのは必至だ。
これは気をつけたい。対策はいまのところない。何度もやってクセつけるしかない。
倍面積を半分するのを忘れる
これもバカとしかいいようがない。
わたしのバカ!バカ!
そこまでのプロセスが合っていても一瞬でパーになってしまう。
これもいまのところの対策としては、戒めに何かに書いておいて、最後に処理するように気をつけるしかない。
式に数値を書き忘れる
これは最初に書いた「独立メモリー」の件と絡む。
間違いではないけども、忘れると、もう一回電卓を叩かなくてはならんということだ。
解答用紙に、途中のプロセスで計算した値を書かなければならないが、書き忘れてしまうのだ。
これもいまのところの対策としては、「身体に染みつけさせる」しかない。
端数の丸め方法が地目に適した方法になってない
これも痛いと思われる。
地目によって端数の丸め方が違うのだ。
まったく違うわけではないんだが、本番では間違いになるんかな?
これは問題文を読んでないから起こる。
勉強進めるとこんな間違いしなくなるんかな?
まとめ
ウルトラ基本的なことみたいなので、早めに矯正したい。
なんか防止法があるのかもしれないが、わたしの知能的にいくと何度もやってしまいそうな事柄ばかりだ。
とりあえずは練習しかなかろう。
「何事も最初からできる人はいない」
これはスタディングの簿記講座で原田先生が言っていたことで、わたしの心に深く残っている言葉だ。
練習練習!
いっしょに勉強しよう!




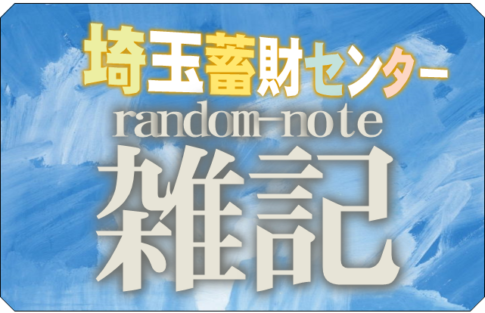
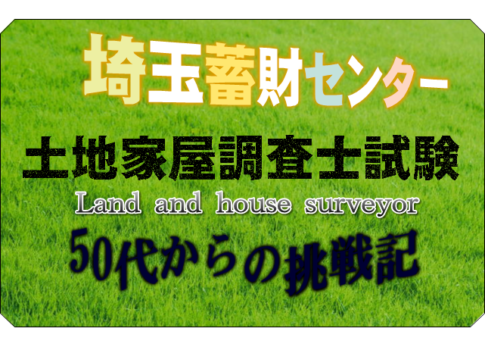
コメントを残す